�@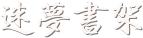
|
�S�l�̟B�@1996�N1���^�u�k�Ѓm�x���X 3�N�Ԃ�̍ēǁB���ɓ��V���[�Y�ň�ԍD���ȍ�i�Ȃ̂ɁA�ēǂ��邽�тɃ��r���[�ɒ����������Ă��܂��̂́A��ނƂ���Ă���w�T�x���A���ɓ����ƒ��P�����̈��o���D�~����������炸����ɂ͗��������˂邱�ƁB�����ēǗ���́A�Z���ȓ��e�ƁA���̖{�̕����������_�I�ɖ�������Ă��܂�����炵���B ���āA����͔����R���ɉB���ꂽ�剾��������ƂȂ�B����̋��G�́A���ɓ����Ђ�ނ��ǂ̑T�̐��E���B ���@�Ƃ������E�̒��Ŏ��X�ƎE����Ă䂭����q�����B���̂��ߓo��l���ɂ��m���������B���R�A���킳����b���T(����)���߂�����e�ƂȂ�B ���ɂ͂�������͂ł��Ȃ����i�j�A��肳��������ׂĂ̔ϔY����������̂ł��Ȃ��炵���B���ɂ��F�X����炵���A�X�g���Ɯ߂������������悤�ɏu���Ɍ����Ƃ��A��傷�����ŏI���ł��Ȃ��A�l�ɂ���Ă͑��⏬�傪���������肵�āA�Ƃɂ����������������C�s�ɏI���͂Ȃ��B �������T�@�ɂ��@�h�������āA�����������T��g�ޏC�s������A��ȏ��������Ă��������ƂŌ��ɋ߂Â��Ă����Ȃǂ�����炵���B����ɁA�u���Ƃ͉����邩�v�ƍl���邱�Ǝ������A����W������̂ł���c�ƂȂ�A�T�ŗ������悤�Ƃ��邱�Ǝ��̂����s�ł���A�Ԉ���Ă���̂�������Ȃ��B �Ƃ����킯�ŁA���낼��o�Ă���T�̍l��(�T�ⓚ)���}�l�ɂ͗���s�\�Ȃ̂ŁA�����������ǂݔ���Ă��܂������Ȃ��Ă��܂����A�E�l�����̓�͂��ׂčl�Ă̒��ɂ���̂ŁA�������Ȃ��Ă�������i�����������c�j�A�����Ɠǂނ��Ƃ������߁B���悢�掖�����I�����悤������Ƃ��A�ǂ̍l�ĂɎ�����Ă����̂����邽�߂ɕK�v�ɂȂ�B ���̋��Ɏ��̔������畬�o�����`����D�~��Ւk�ɂ́A�����Ȃ��爳�|�����B����ɖ{�Ƃ͊W�Ȃ������Ȃ���炪�����̔w�i�Ƃ��čI���ɍ\������Ă���B�܂�A���̍�i�̖ʔ��݂͍I���ɒ��菄�炳�ꂽ�����ɂ���B�œ_�̓g���b�N�ł͂Ȃ��̂��B �`���́u�ّm���E�߂��̂��v�̃C���p�N�g���������A�����ꂽ�R�̒��ŏC�s����m���������R�Ƃ����p������Ă������܂��ʔ���������āA���łɓ���݂̓o��l���ł���|�ؒÂ����@�U��͈ꕞ�̂�����U��T���A���x�낤��������������Ɗy���߂�B ���A���̍�i�ł̂��ɉ|�ؒ×������K�N�\���c�̉��l���T�㏕��Ƃ��Ċ��邱�Ƃɂ���v�c���A�Y���Ƃ��ď��o�ꂷ��B���ɓ��ꖡ�ɏo���������ɔނ͓��݊O�����Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B���̊O�`�w�S��k�R�܁x���̕�����Ղ肪���܂����̂ŁA����ēǂ��Ă��ĕ��C�ɂƂ�ꂽ�B���X�y���Ƃ͂����^�ʖڂŎd���M�S�ȎႫ�Y���������̂Ɂc���ƈ����i�j�B �ȉ��]�k�B �w���x��덆�i�p�쏑�X�j�����̒���V�ꎁ�Ƃ̑Βk�ŁA���Ɏ��͎��g�������������ɂ������āu���c�S���܌��M�v���ӎ������v�Əq�ׂĂ���̂�ǂ�ŁA�����������������B �ނ̕��̂͂ǂ����ÐF���R�Ƃ��Ă���A��i�̎���w�i�̕��͋C���������Ă���B ���_�A���{�ߑ㕶�w�ȍ~�̖|��̂�ϑ̊����Ƃ�������悵�Ă���A�����ăR���g���[�����ꂽ�����I�ȕ��̂ł���B���Ɏ�����g���閯���w��d���k�`�Ȃǂɂ��A���̓Ɠ��ȕ����̃��Y�����傢�ɉe�����āA���ǎ҂����f������B�L���ȕ\���͂��A���Ɏ��̓S�ʔ�����E�Ɍ�������^���Ă���̂��낤�B 2001�N9���w���ɔ� �S�l�̟B�x�A2005�N10������w�������ɔ� �S�l�̟B�i1�`4�j�x�u�k�����ɂ��o�Ă���B |
�o���ɉE�q���@1997�N6���^�������_�Ё^��25��ԕ��w��� ���`�[�t�́w�l�J���k�x�����A����͉��k�ł����O�b�ł��Ȃ��B�����������B�Ȃ�Ƃ��������A�ł�������A����قǂ܂łɔ������A���낵������ɂ͖ő��ɏo��Ȃ���������Ȃ��B ��l���̐ۏB�Q�l�E����ɉE�q��́A����g���S�E���J�����q��̖��A����̂��Ƃɖ��{�q�ɓ���B��͕a�������A���̌��ǂŐ����̔��e���X������Ă��邪�A�����p���邱�Ƃ̂Ȃ��C��Ȑ��i�B �ɉE�q�厩�g�A���̗e�p�ɂ͂�����炸�A��������܂ʼn�������Ƃ����Ȃ������Ȃ����������v���͂��߂�B����܂��A�������ɈɉE�q��Ɏ䂩��Ă����B�����A�ӂ���̈Ӓn�̒��荇���Ɗ���̂���Ⴂ����v�w����������A����������g�^�͂̈ɓ��앺�q�ɂ����܂�����܂��B �앺�q�̛@�v�ɛƂ�����͕v�̂��߂ɂ悩��ƉƂ��o��B�ɉE�q��͊앺�q�̎q��s�������E���~���łɉ���������B�ɉE�q�傪�K���ł��邱�Ƃɖ������A�n�������[���������X���߂����Ă�����B�����A�₪�Ĉɓ��̛@�v��m��A��͋�������\�\�B ����͊e�͂��Ƃɐݒ肳�ꂽ�o��l���̎��_�Ői�s����B�ɓ��앺�q���߂��閔���E�q��A��A������̊m���ƍ��d�J�ɕ`���Ă������ƂŁA�Ȗ��ɒ���ꂽ�������A�I�͂Ɍ������Č������A�����A�������Ă������܂́A���ɉĕF���̏\���ԁB�ł��A�����炭�u���ɉĕF��i�v�Ƃ��Ă̍D�݂͂͂����蕪�����Ǝv���B�w���ɓ��V���[�Y�x�̃C���[�W��O���ɒu�����ǂނƁA���܂�ɂ����������Ⴄ��i�Ȃ̂ŖʐH�炤��������Ȃ��B ��҂͈ɉE�q��������Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�^���ɖ|�M����闝�m�I�ȑP�ӂ̐l�Ƃ��Ă�`�����ƂŁA�l�Ԃ̋Ƃ̐[���̋��낵���A�����Ĉ�������`���Ă���B���S�ŏd�ꂵ���A����ł��Đ�捂ȕ���ł���B ���X�g�ŏ��߂��w�o���ɉE�q��x�̃^�C�g������������ƈӖ������̂����A���̐Â����������������������B |
�A�����S�����@2003�N8���^�u�k�Ѓm�x���X �����ΔȂɁA�����̒��̔����Ŗ��ߐs�����ꂽ�u���̊فv�ƌĂ��m�ق�����B�ق̎�l�ł��錳�E���݂̗R�ǝ�ȂƂ��Č}���������́A�������̗����K���E�����Ƃ����ߌ��������B�T�x�ڂ̍�����O�ɁA���݂͒T��ɍȂƂȂ�l�̌�q���˗����� ���̒T�オ�A(���ɂ������)���̉|�ؒ×��Y�B����̔ނ͖ڂ������A�̒��͐�s���B���������Ɋقɓ��s���邱�ƂɂȂ��Ă��܂�����Ƃ̊��F�͌˘f�����衊��̍��f��������̂��Ƃ��A�|�ؒÂ͊قɓ���Ȃ袂����ɐl�E�������飂ƒN�ɂƂ��Ȃ��錾���� �ނ�͉ԉł���邱�Ƃ��o����̂�������ċ��ɓ������T���H�F�͜ߕ����ǂ����Ƃ��̂��\�\� �{��́A�V���[�Y�L�����̊��F�A���݂��ƗR�ǝ��A�����āu���̊فv�̉ߋ��̎����Ɋ���������Y���ɒ��l�Y�́A�����́u���v�ɂ���l�̌��ō\������Ă���B���ɍ�i���O��ɂ�����ʂ�A���̎�@���N�Z���m�B�܂�A�킸���Ȍ��t���ꗂ�B���ȋL���A�o����m���̌�T���d�˂Ďd�|����ꂽ�S���g���b�N����{�ɂ���B������u���v�������e�͂��ׂĉ��^�I�Ɏ~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�v���Ԃ�ɔ]�݂����g�����C�������ǁA��������͋��Ɏ��A�����ȒP�Ƀ{���͂����Ȃ���ˁB ���e�I�ɂ͏��Ղ��猋�\��_�ɕ����������Ă���̂Ť���قLjӊO���͊������Ȃ��B�����g�P�^�R�قǓǂƂ���ŕ���̂W�������͑z�������Ă��܂������A�����w�I�m������������Β��Ղ̋��ɓ��̉�b�Ō����������낤�B�������}���e�B���E�n�C�f�b�K�[�́u������`�v�Ɓu��w�v�Ƃ����َ��Ȏv�z���������킹�A�Ǝ��̗��_�֓����A����Ɏ����̓��@���ƓW�J�����Ă������Ɏ��̌��|�͑��ς�炸�I�݂��B ��i���т��e�[�}�́u�v�B���́u�����ρv�̑������𗍂߁A���͋��Ɏ��́A�쒆�Œ�c���Ă���A�T�㏬���͂Ȃ��u�E�l�v����ʂȂ��̂Ƃ��Ĉ����̂��A�Ƃ��������������グ�悤�����Ă����̂�������Ȃ��B���������ǂݕ�������ƁA�Ǐ���Ԃ̂Ȃ��Ő��܂��������قȃL�����N�^�[�����̂��߂̓���ĂɂȂ��Ă��܂��Ƃ��낾���A�Ȃɐ旧���ꂽ���Y���E�ɒ���u�����ρv�Ɨ��߂邱�Ƃŏd���Ȍ����������o���Ă���B ����Ȃ킯�ŁA�{��͍��܂ł̋��ɓ��V���[�Y�Ƃ�����Ɣ��G�肪�Ⴄ�B�������̂��̂������قȃL�����̑��݊��̕�����ې[���A���̃V���[�Y�ɋ��ʂ���d������������悤�Ȏd�|�������X������Ȃ��B�łंȂ�Ƃ����Ă����C���f�B�b�V���͋��ɓ��̜߂������Ƃ��B��X�Ɛ�������A�[���������Ă��܂�����������(��)� �Ƃ���Ŏ��́A�ɂ��₩�����N�T��E�|�ؒÂ���̃t�@���ł���B����͈ꎞ�I�Ƃ͂����Ӗ��ƂȂ��Ă��܂����Ƃ������āA���܂芈��(�����~���H)�̏ꂪ�Ȃ������̂��c�O�B�Ƃ͂����A�|�ؒÂ���͂ǂ��܂ł����Ă��|�ؒÂ���A����͂�����Ƃ���ǂ��������ǁA����Ȕނ����������`�B ���łȂ���A����������Ƃ����o�ꂵ�Ȃ��ϑԂȗ����Ď@��̉B��t�@���\�\���X�ƌ����Ȃ����߂��������邩��\�\�ł��������肷��(��)�B |
�S��k�R�܁\�J�@1999�N11��10���^�u�k�Ѓm�x���X �~���悤�̖��������ǂ���̏��A���ۓI�Ȗ��������A���f�s�\�ȉ����ۂ��A�S�� �����S���ӂ���j�B�������A�T��E�|�ؒ×��Y�I�@�u���l�v�̊��A�v�c�A����A�ɍ��Ԃ������A��āA����ɂ͋��ɓ��E���T���H�F������������o���āA���������̑�\��I �s�\��ŊJ����͋Z���y��O�{�̒��ҁB�\�\�{���J�o�[��"���ē�"���炵�Ă����킭�����Ă����Ƃ������́B ������`�Ȍ��ؑ��ł���A������̌䑂�q�ɂ��Č��C�R�G���[�g�m���A���܂��߂��ۂ������A���͂ƈ��������ɐl�̋L�������邱�Ƃ��o����Ƃ����ٔ\�����\�\����A����������̔��e�ƒn�ʂE�����Ă��܂��j�V���Ȑ��i�ƌ����Ƃ������������������낤�\�\�u�_�v�����āu�T��v�ł���|�ؒ×��Y�𒌂ɁA�V���[�Y�I�[���X�^�[�L���X�g���A�z���H���̐}�������E�{���̎��_���Ԃ��Ă���B �|�ؒÂ͍r�Ԃ�_���B�ނ̎���ɏW�܂��Ă��镨�D���́A�u�_�v�ł���ނɂƂ��Ắu���l�v������B�|�ؒÂ̍s���Ƃ���A�l�͉����R������A�함�͊����Ȃ��܂łɕ��ӂ���A���l�������E���������Ă��邤���Ɏ����͓��˂ɉ��������B���̋��ɓ����ƒ��T���H�F�ł���A�ۉ��Ȃ��������܂�A�ԂԂƕs���������Ȃ�����T�|�[�g������Ȃ�����ɒu����Ă��܂��B�Ȃ��ĒT��̑��݂��̂��̂��s�𗝂Ȃ̂�����A���������ƍ߂Ȃlj��ق��̂��̂��Ǝv�킳��Ă��܂��B �����|�ؒẤA�����V�ߖ��D�ŖT�ᖳ�l�Ȃ����̒j�ł͂Ȃ��B���݂����A�l�|��������W���Ă��܂����l��A���ꂾ�����D�~�j�ł��鋞�ɓ����A�������߂Ȃ�����t�������Ă����������̖��͂�����͂��B�U�����C�ɂȂ�Η��h�Ȍ䑂�i�ɂȂ��Ƃ�����݂�ƁA�����炭�|�ؒẤu�������v�l�ԂȂ̂ł͂Ȃ��A��l�������Ȃ��͂䂦�A��l�ɂ͕�����Ȃ��d�����̂�w�����Ă���̂��B���Ƃ̊j�S�����͌����Ă��܂��̂�����A����̐l�Ԃ��E����������l���A�z�炵�������邾�낤�B�l�ԊW�������������Ȃ��Ă��܂��̂��d�����Ȃ��̂��������Ȃ��B���̏�A��������J���ɂ��ނ���i�ʓ|�Ȃ̂��낤�A���Ԃ�j�A�e�ڂ��U�炸�A�ނ̌������̂Ɍ������ĂЂ�����簐i���Ă����B����䂦�A��l�ɂ͔j�V�r�ȍs���A�����ɂ����v���Ȃ����A�Ђ�����Ђ������܂킵�Ă���悤�ɂ��������Ȃ��̂��B �Ȃ�̒k�����Ȃ��|�ؒÂ̌����Ƃ���Ƃ���𗝉����Ă��܂����ɓ����A�܂�͓����������W�i���Ă킯�ŁA�ގ��g���ǂ�Ȃɔے肵�Ă��A�K�N�\���T��ꖡ�ɂ͈Ⴂ�Ȃ�(��)�B �V���u�S��k�R�܁\���v���ł��̂ŁA���łɍēǂ����̂����A���̃V���[�Y�͊O�`�Ƃ�������A���ȃp���f�B�I�ȗv�f�������A�o��l���̐��i���R���f�B�I�ɕ`����Ă���B �Ƃɂ����e�����Ղ肪������|�B���l�������ے肵���T��ɖ��f����Ă��܂��Ă���A�l�̐S�̂܂܂Ȃ�Ȃ��ɋ���A�u���l�v�̗ނł���ǎ҂̋����𑶕��Ɋy����ł��܂����ق��������Ƃ������́B�u�_�v�ɂ��������ł��Ȃ������������ɂ���B |
�S��k�R�܁\���@2004�N7��5���^�u�k�Ѓm�x���X ����w�S��k�R�܁\�J�x�ŃV���[�Y�]������Ă��܂����̂ŁA������͂����Ƃ��ē��B �u�������{�������������Ȃ��B�����^������̂݁I�@���ڏG��A�r�͍ŋ��A�V�����G���K�N�\���T��E�|�ؒ×玟�Y�v�V���[�Y���e�̒��јA��W�B�O�쓯�l�A�z���H���̐}�ʈ����E�{���̎��_�ŕ`����Ă���B ���ɓ��́u�d���V���[�Y�v�̂悤�ȉA�S�ŕ��G����ȓ�͖����A�ނ���u����̓�v�I���������[�Ƃ������P�������X�g�[���[�ł���B�K�N�\���T��ꖡ�B��̏펯�l�A���ɓ�(�{�l�͊�Ȃɔے肵�Ă��邪)�̓�����͑����ɍς܂���A�T��T�C�h�������̍����ɑ��ăg���b�v���d�|����W�J���ʔ����B�O���ǂ�ł�����ɂ͍��X�����s�v���낤���A�Ƃɂ����|�ؒÂ��\����B����̃L�[���[�h�́u�ɂ�v���H�I ���^��́A�܂˂��L�����[�Ŗ��炩�ɂȂ�S��Ƃ́H�@�|�ؒÂ̎x���ŗ�E�T�ᖳ�l�Ԃ����Ⴆ��u�ܓ��L�v�A�|�ؒÂ̈ٔ\���t��ɑO���̕��Q����Ă�슴�T��E�_���������Y���|�ؒÂ��Ό�����u�_�O���v�A�̖ʂ̓�Ǝ��͂Ŋ����N���铐����𗍂߂��u�ʗ��C�v�̎O��B �{���i�l�j�͎�������߁A��x�Ɖ|�ؒÂɊւ��ʂƌ��S���Ȃ���A�������܂�Ă��邠����A�����ۂ������Ƃ������c�c���������ɒ��߂��܂��A�N�B ����͉|�ؒÃp�p���o��B�\�̕ϐl�Ԃ�A���Ƃ������Ƃڂ����_���f�B�Ԃ���I����B ���X�g�ʼn|�ؒÂ��u�_�v�炵����ʍs�����Ƃ�̂ŁA������V���[�Y�I�����Ƃ�����ƃh�L�b�B �Ȃ�Ɖ��l���ԘJ���悤�Ƃ����̂����A�����͉|�ؒÁA�ނ�̈Ԃ߂ɂȂ�̂��ǂ���(��)�B �����͏��X�����̊������邪�A�w�A�����S����x�ł��ƂȂ��߂̉|�ؒÂɏ����s�NjC���������t�@���ɂ����߂���B |